
|
|
第七話 黄金の雷(14) 【 第七話 黄金の雷(14) 】 こうして、幸運にも、皇子マリアノは無事にアンドレスの陣営に辿り着くに至ったが、他方で、トゥパク・アマルらの囚われているクスコの牢獄では、いよいよ差し迫った状況が展開していた。 アンドレスの元にマリアノが到着するよりも少し前の話に戻るが、トゥパク・アマルらが投獄されて6日目の頃、彼らの収容されたクスコの旧イエズス会修道院では、ついにトゥパク・アマルら家族への過酷な訊問――訊問とは言え、その内実は、結局のところ拷問である――が開始されたのである。 この訊問及び拷問を担当したのは、ペルー副王領の首府リマにあるアウディエンシア(最高司法院)の聴訴官、ベニト・デ・ラ・マタ・リナレスという博士であった。 このマタは、実際、サディズムの権化のような人物であったと言われるが、敢えてこの男を、この忌まわしい役目の担当官として抜擢した巡察官アレッチェこそ、真にサディズムの権化であったと言いたい。 兎も角も、このマタという聴訴官は、トゥパク・アマルを中心に、その家族たちに連日のように激しい拷問を繰り返した。 スペイン側の役人たちがトゥパク・アマルから聞き出したかった情報は――次男マリアノの行方は?そのマリアノを匿(かくま)っているのは誰か?現在は誰がトゥパク・アマルの後を受けて反乱を指揮しているか?この後の反乱の展開のために、既に何か策を施しているか?どのように、いつから反乱軍を組織したか?反乱に加担している同盟者は誰か?当地生まれの有力なスペイン人の中に共犯者がいるか?――などであった。 だが、トゥパク・アマルも、そして、妻ミカエラも、息子たちさえも、何一つとして真相を明かそうとはしなかった。 そのような状況下で、マタの加える拷問は、いっそう復讐めいた要素を孕(はら)みながら、日増しにエスカレートしていった。 スペイン本国出身の博学多識な学者であり、且つ、首府リマの最高司法院のエリート高官であるということに強い自負を抱いていたこのマタにとって、己の訊問に対して決して口を割ろうとしないトゥパク・アマルらの態度は、己に対する断固たる侮辱とさえ感じられていた。 「下の階級」の「インディオ」が思い通りにならぬというその苛立ちは、酷い屈辱を受けているという彼の勝手な憶測や被害妄想を、日毎に刺激していった。 結果、拷問の付加が重くなるばかりでなく、次第に拷問の加えられる時間帯さえもが、早まっていく。 この日も、朝早くから、彼の悪魔の所業が行われようとしていた。 4月29日早朝午前4時、マタはトゥパク・アマルを薄暗い拷問部屋へと連れてこさせた。 高地の秋の冷え込みは既に冬並の厳しさだが、まだ日も昇らぬ、しかも、地下深い獄中の空気は、冷気の淀んだ水底のように凍てついている。 訊問が開始された4月22日以来、1週間以上に渡って続けられてきた連日の過酷な拷問の繰り返しで、トゥパク・アマルの肉体は既にかなり疲弊しており、牢からその部屋までも、マタの部下たちに引き摺(ず)られるようにしながらの移動であった。 だが、トゥパク・アマルの、その眼光は以前と全く変わらず鋭く冷静沈着で、これから己に課せられるであろう残忍な拷問具を目前にしても、表情一つ動かない。 そんなトゥパク・アマルの様子を、その場に立ち会っていたアレッチェが、やや離れた壁際の一隅から、あの氷のような冷血な目で見つめている。 マタは神経質そうな顔面を興奮気味にひくつかせながら、トゥパク・アマルの方へと居丈高に近づいていく。 肉体的疲弊のために、もはや自力では立っていられず、冷え切った石の壁に寄りかかるようにして姿勢を保っているトゥパク・アマルの前に、マタは尊大な足取りで立ちはだかった。 壁にもたれていながらも、長身のトゥパク・アマルはマタを見下ろす形になっている。 今、そのトゥパク・アマルの、以前と変らぬ、否、以前にも増して達観し切ったような研ぎ澄まされた切れ長の目は、この破廉恥行為を繰り返す眼前の西洋人を哀れんでいるようにさえ見える。 マタはいっそう苛々と体を揺すりながら、殆ど張り倒したいほどの衝動を覚える。 しかし、上官であるアレッチェの監視の目を背後に意識して、懸命に己の衝動を抑え込んだ。 そして、いかにも学者ぶった慇懃(いんぎん)な仕草で記録表に何かを走り書きすると、蔑むような目つきで眼前の「インディオ」を一瞥した。 マタの、苛立ちと憤怒を押し殺した、しわがれた声が冷たく響く。 「あらかじめ言っておくが、これから行うことによって、おまえが死のうとも、あるいは、片端(かたわ)になろうとも、それは全て、真実を言おうとしなかったおまえ自身の罪だ。 そのことをよく覚えておけ。 よいな…――だが…」 マタは意味ありげに、息を継ぐ。 「あるいは、おまえが、今、ここで全てを白状する気になったと言うのならば、まず、その話を聞いてやってもよい」 だが、トゥパク・アマルは、「話すことは何も無い」と、全く感情の伴わぬ無機質な声で応えたのみだった。 マタは、屈辱に震える拳を握り締める。 同時に、部屋の一隅からは、アレッチェの刺すような冷酷な視線が、トゥパク・アマルにではなく、むしろ己の背中の方に注がれているのを感じ、マタはひどく焦りを覚えた。 マタの首筋に、冷たい汗が滲む。 このマタは、散々の拷問を続けながらも、トゥパク・アマルから何ら情報を引き出せぬことを、上官であるアレッチェから繰り返し咎(とが)められていたのだった。 (今日こそは、トゥパク・アマルの口を意地でも割らせねばならぬ…――!!)  マタは、乾ききった己の唇を舐めた。 そして、悪魔のような声で「やれ」と、部下に指示をする。 役人たちは、トゥパク・アマルの両手首を背中で縛り、縛った紐を両足首に結びつけた。 そして、その紐に100ポンド(約45.4キログラム)の鉄棒を結びつけて、彼の身体を1メートル50センチ程の高さに吊るし上げた。 全く、拷問を加えている方が目を覆いたくなるような、あまりにも残酷な光景であった。 この所業には、あの冷酷極まりないアレッチェでさえ、瞬間、僅かに視線を斜めに落とした。 アレッチェにしてみれば、まさか、このような形で本当にトゥパク・アマルに死なれたら、それこそ非常に不都合でもあったのだ。 トゥパク・アマルは、公衆の面前で、しかるべき形で、処刑にされなければならぬ、とアレッチェは考えていた。 …――そう…反乱軍の残党を心底震撼させ、この後、この国で反乱を起こそうなどとする輩(やから)のニ度と現れぬように、その「見せしめ」として…――!! 拷問の渦中にあるトゥパク・アマルの方に、アレッチェの氷のような視線は、再び、じっと執拗に注がれる。 一方、トゥパク・アマルは、その想像を絶する苦痛の状態におかれても、時に呻き声を漏らすだけで、全く口を割ろうとはしなかった。 相変わらず、ただ残虐なだけの、不毛な時間ばかりが流れていく。  いかにトゥパク・アマルが強靭な肉体を持っていようとも、さすがに、これ以上の付加の持続は限界だ、と、アレッチェの方が思った瞬間、しかしながら、トゥパク・アマルの無言の様(さま)に、激しい侮辱感の極みに達したマタが、「もっと錘(おもり)を加えよ!!」と常軌を逸した指示を出す。 だが、この時は、アレッチェが鋭くマタを制した。 「馬鹿め!! 良く見ろ」 アレッチェが苛立ちながら指し示す先には、錘を縛りつけられたトゥパク・アマルの不自然に大きく婉曲した腕があった。 「トゥパク・アマルを、さっさと下ろすのだ!!」 アレッチェの激しく責め、咎(とが)めるような剣幕に、マタの部下たちが慌ててトゥパク・アマルを床に下ろす。 「既に、骨の関節が外れている」と、刺すような声で言うアレッチェは、トゥパク・アマルの右腕を指差してマタを蔑むように見た。 トゥパク・アマルの右腕は、無残に脱臼していたのだ。 それでも苦悶の気配など微塵も覗(のぞ)かせぬトゥパク・アマルの様子をアレッチェは一瞥すると、感情を押し殺した声で言う。 「何という強情な…。 いつまで、このような手を焼かせるつもりだ」 さすがのトゥパク・アマルも、吊り上げらた状態から下ろされたままの姿で、疲弊しきったその身をぐったりと冷たい床に横たえている。 だが、顔にかかった乱れた長い黒髪の間から覗く切れ長の目は、相変わらず、何事も無かったように沈着な鋭い光を宿したまま、ただ無言でアレッチェの顔を見上げている。 ――そなたこそ、いつまで、このような不毛なことを続ける? このような形で、わたしが何か話すと本気で思っているのか?―― トゥパク・アマルの目がそう語っているかのような激しい感覚に憑かれ、アレッチェは噛んだ唇を醜く歪めた。 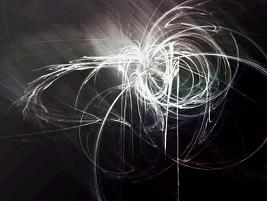 アレッチェは、腕の状態を観察するような素振りで、その長い足の靴先だけで、無造作にトゥパク・アマルの脱臼した腕を幾つかの角度から動かした。 その乱雑な動かし方は、周囲から見れば、まるで相手を甚振(いたぶ)っているようにしか見えない。 黙々と硬く冷たい靴先を動かすアレッチェの全身からは、苛立ちなのか、憎しみなのか、屈辱感なのか、いずれにせよ、どす黒いオーラが発せられているようでさえある。 他方、トゥパク・アマルは、あの眉一筋さえ動かぬ沈着な表情のまま、まるで相手を哀れんでいるかのような気配さえ湛え、これまでも、今も、愚かな所業を延々と続けている頭上の西洋人の様子を観察している。 やがて、アレッチェは氷のような靴音と共に背を向けると、「腕はそのまま放置しろ」と吐き捨てるように言い残し、その場を去った。 だが、この時は、さすがのアレッチェも、トゥパク・アマルの態度を憎々しく思う反面、その内心では、密かに感じ入るところがあったようだ。 実際、翌日の4月30日に歴史上の彼がインディアス枢機相宛てに送った手紙の中で、次のように書き記された文言が、今も歴史上の資料として残されている。 ――『トゥパク・アマルは非常に頑健な魂と肉体を持ち、はかり知れぬほど沈着である…!!』―― ◆◇◆ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ第八話 青年インカ(1)をご覧ください。◆◇◆ |